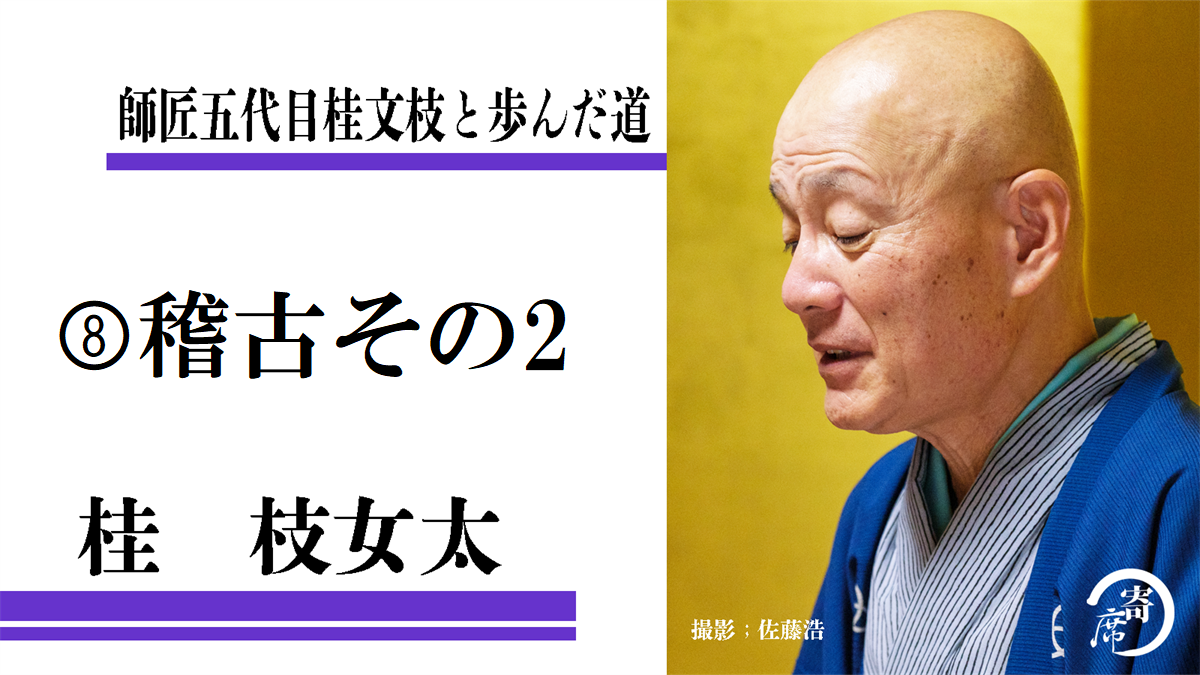落語家にとって落語の稽古は大切な仕事です。この稽古がないと高座に上がれませんから。上がったとしてもお客さんから「金返せ」なんて言われてしまいます。
桂枝女太師匠もプロの落語家になったのだから、プロの稽古を体験したいと考えていました。ところが……。一門によってカラーの違う落語の稽古、五代目桂文枝師匠の稽古はどのようなものだったのでしょうか。お楽しみください!
稽古その2
最近、若手の落語家に稽古をつけることが多くなった。
私自身に弟子はいないが、他の一門の若手の子がちょくちょくやって来る。
頼りにされていると思えば嬉しい気にもなるが、私自身、師匠に稽古をつけてもらったことがほとんどない。
つまり稽古のつけ方がよくわからない。いつも手探りの状態だ。
稽古をつけてもらったことがまったくないわけではない。ただ、いちから、つまり全く白紙の状態からつけてもらったことは一度もない。
なのでそういう状態からの稽古はどうしたものかわからない。
私の師匠はこちらからお願いしないかぎり絶対に稽古しようとは言わない人だった。
こちらからお願いしても「わしのテープで覚えといで。覚えたら聞いたるわ」。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
最初のうちはこの稽古方法ならオチケンのときとほとんど変わらないので楽だと思ったのだが、そのうちに「あれ?」と思うようになった。
「ひょっとして俺はあまり見込みがないので適当でいいか」と思われているのではないか・・・疑心暗鬼というか、はっきり言って「ひがみ」。
しかし「ひがみ」というのは、あきらかに他の人と差別あるいは区別されて初めて感じるもので、私の場合は少し違う。他の人のことはまったくわからない。なぜなら同門の先輩でも私の弟子期間中の3年間に稽古に来た人は一人しかいなかったのだから。
ちなみにその一人とは今の六代文枝さん、当時の三枝兄さんだった。
ネタは「蛸芝居」。無論いちからの稽古ではなく、きっちりと覚えて師匠に見てもらうという一回きりの稽古だ。
二階の座敷での稽古を階段の途中で聞いていたことを昨日のように思い出す。
だからこれは単なる思い過ごしなのだが、入門前に想像していた弟子生活とはかなり違うので戸惑っていたのだろう。
一度「東の旅・発端」というネタの稽古をお願いしたことがある。
このネタは笑うところは一箇所もない。新人の口慣らしというようなネタで、まるで早口言葉のように決まった台詞を張り扇と小拍子で見台を叩きながらただただ喋っていくという落語で、噺家になったらまず最初に教えてもらうのがこの噺だというのが落語の世界での常識になっているネタである。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
あるときクルマの中で「おまえ、どんなネタがしたいねん」と師匠の方から聞いてきた。
珍しいこともあるな、稽古つけてもらえるんやと思ったので、「発端をお願いします」。
師匠の返事を聞いたとき、クルマをぶつけそうになった。
「そんなおもろない落語覚えて、どこでするつもりやねん」
たしかにおっしゃるとおり、やれるところなど・・・無い。
なんか、思っていた落語家の世界とは随分と違うなと思ったが、なぜか新鮮な気分というか、これがプロの世界なんだと妙に高揚したのを覚えている。
師匠の稽古はなんというか、最低限のことはアドバイスしてやる、あとはお前自身が舞台で恥かいてちょっとずつ良くしていけ。そんな稽古だったんだと思う。